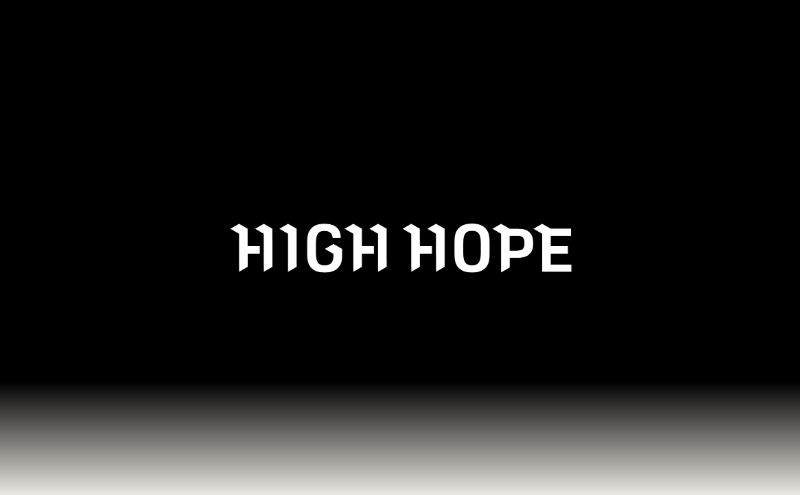多摩少年院で暮らす少年たちとの出会い。彼らからもらった希望。

6人の少年は、背筋をぐっと伸ばして、大きな大きな声で、真っすぐにこちらを見て「ありがとうございました」と言った。この時間が終わってしまう。「握手をしてもいいですか」と法務教官の先生に聞いた時、隣の二人ももう手を差し出していた。一人ずつ両手をしっかりと握り、「がんばりましょう」「応援してます」と言葉を交わし、きれいに整列して教室を出て行く彼らの背中を見送った。
2024年11月。プロサッカークラブ FC東京の方々と多摩を訪れ、初めて少年院の中で「HIGH HOPEプログラム」を実施した二日間のことを、上手く言葉にできないまま数週間が過ぎた。軽々しく感動したなんて言っていいのだろうか、たまたま起こった奇跡のようなできごとだったのかもしれない、あの涙はいったい何の涙だったんだろう……そんなことを考えながら、また目の前の仕事に明け暮れた。
12月に入り、少年たちの感想文がWord文書になって届いた。温度を持った言葉が、名前が伏せられていても顔が浮かぶような文章が並んでいた。スクロールするたびに胸がいっぱいになって、あの日の様子が思い出された。
あなたが目標を達成すると、誰がどんな気持ちになりますか。なってほしいですか。
実現にいたるまでの調整に何ヶ月もかかり、何度もプログラムを組み直して、たどり着いたテーマは「夢・目標」。人材育成の第一線で活躍する原田 隆史 先生のメソッドを土台にさせていただき、「その目標を達成して、あなたはどんな気持ちになりますか。なりたいですか。」「あなたが目標を達成すると、誰がどんな気持ちになりますか。なってほしいですか。」という問いを、少年たちに投げかけた。
「夢・目標」について話すためには、何よりもまず、私たちとのプログラムが彼らにとって安心して発言できる場にならなくてはいけない。ICHI INC.の中馬 一登とFC東京の石川 直宏 さん、まずは二人の大人がそれまでの人生をさらけ出した。これだと思える夢が見つからず17年もの間、探し続けたこと。悔しさ、情けなさ、ムシャクシャして一人でボールを蹴り続けたこと。背中に羽が生えたような感覚でプレーできた試合。
かたい表情で教室に入ってきた少年たちは、最初は感情の読めない目をしていた。「正直、何をするのかわからないし、はじめは乗り気じゃなかった」と後で話してくれた子もいた。中馬と石川さんの働きかけに呼応して、徐々に目線が意志を持ち、一つひとつの言葉への反応に熱がこもっていくのがわかった。30分ほど経った頃には、彼らも私たちも肩の力が抜けて、笑顔が出始めた。
講演というかたちではあったけれど、あの場でのやりとりはすごくフィジカルで、少年たちは二人が全身から発するものを懸命に受け止めていたように思う。最後に全員で円になって、一人ずつ感想を聞かせてもらった。励みになる言葉をたくさんもらって、曇り空の中、駅までの道を歩いた。
自分の思いや考えを、先生や周りの人に素直に伝えてみた
それでも、宿に戻って翌日の準備をしている時は心配な気持ちもあった。みんな宿題をちゃんとやってくれるだろうか、ほとんど書けていない子がいたらどうしよう、明日になったらまた表情が変わっていたら……期待と不安をどちらも感じながら、発表での画面の使い方や対話の進め方を見直した。
そして2日目、少年たちは私たちの予想を思いっきり飛び越えていき、想像もできなかった景色を見せてくれた。ここまでの道のりは長かった。民間企業が少年院の中で継続してプログラムを実施するという取り組みは日本では前例がなく、何度も計画が頓挫しかけ、そのたびに一喜一憂し、仮説と想像しか重ねられない日々が続いた。でもこの日、彼らは次々に、手をぐっと伸ばせば掴めそうな、くっきりとした夢と目標を私たちに聞かせてくれた。
22歳までにこの資格を取る。
憧れのあの有名人と会って話したい。
保護観察期間が切れたら、海外旅行に行く。
余白のある大人になる。
飲食店を経営して、母子家庭や生活保護の人にあたたかくおいしいごはんをおなかいっぱい食べさせる。
出院後1年以内にギターをひけるようになる。
「この夢は、誰にも言ったことがなかったです。直前まで迷って、宿題の紙には書かなかったんですけど、今日初めて人に言いました」という子もいた。
「あなたが目標を達成すると、誰がどんな気持ちになりますか。なってほしいですか。」という問いに対しても、紙いっぱいにたくさんのあたたかい言葉が書かれていた。
正直なところ、彼らがしっかりと自身の考えを言葉にできることにまず驚いた。少年院で彼らは日記を毎日書き、先生たちがコメントを返すという。そのやりとりの中で、言語化の力が培われてきたのだと思う。法務教官の先生たちだけでなく、警察や裁判に関わった方々など、少年院に来るまでの過程で出会った大人たちからも、彼らの将来を思っての働きかけがたくさんあったのだろう。
石川さんの話を聞いて、さっそくその夜、自分の思いや考えを先生や周りの人に素直に伝えてみた、という少年もいた。きれいごとじゃないかと思ったけれど、寮に帰って実践してみると本当に相手の反応が変わった、と。昨夜起こったことを確かめるように、そう教えてくれた。

「人の夢を応援できる人間でありたい」
毎年1,000人を超える若者が、少年院を出て社会へ戻る。親や親戚のもとへ帰る子もいれば、地元を離れて知らない土地の更生保護施設に入所する子もいる。仕事は見つかるだろうか。少年院にいたことがわかったら、周りの人はどんな反応を示すのだろうか。様々な不安があると思う。ここに来る若者の多くは壮絶な虐待やいじめを経験していると考えると、なおさら。
法が定めたルールがあり、これから彼らがどの都道府県へ行くのか、誰と暮らすのか、私たちは知ることができない。彼らがどんな罪を犯したのかもわからない。
そんな中、
「将来、店を開けたら、この名前を見て僕のことを思い出してもらえたら」
と言ってくれた少年がいた。
「いずれあの方々に会いに行き、良い姿をみせたいです。」
と感想文に書いてくれた少年がいた。京都に戻ってからも、何度もその言葉を噛みしめた。
彼らにとっての希望を生み出すために多摩少年院へ行ったつもりだったけれど、私たちが彼らからたくさんの希望をもらったのだった。
「人の夢を応援できる人間でありたい」と、開始の時点では誰よりも斜に構えていた少年が話してくれた。法務教官の方も「表情がずいぶん変わりましたね」とおっしゃっていた。

誰かの役に立つことにやりがいを感じ、社会に貢献する人になってほしい
感想文の中に、こんなことが書かれていた。
「最後には泣いて感想を言っていた中馬さんを見て本当に努力してこのプログラムを作り今回初めてやって上手くいって、そしてみんなの笑顔を見て凄く嬉しかったと思う。本当に参加できて良かったです。」
私たちのことを気にかけてくれる優しさを感じ、これを書いてくれたのは多分あの子だろうなと、彼の印象的な瞳を思い出す。罪を犯した少年の、優しさ。こう書くと、違和感を持つ人、どう受けとるべきか悩む人が多いのではないかと思う。一方で、たとえどんな罪を犯したとしても、人の心の中から優しさが完全になくなることは、私には想像がしづらい。
「こわい」「危ない」「できれば関わりたくない」というイメージが一般的で、加害者支援に対する批判はきっとなくなりはしない。そんな社会全体の空気を変えていくことも、再犯を減らすためには必要不可欠だと私たちは思っている。
京都に戻った翌週、『あふれでたのはやさしさだった 奈良少年刑務所 絵本と詩の教室』という本を教えてもらった。2007年から9年間、少年刑務所で講師を務めた作家の著書には、プログラム終了後の私たちの会話とよく似た心情が綴られていた。
友からやさしい言葉を浴びた少年たちは、わたしの目の前で変わっていった。まるで蛹から蝶になるように一瞬にして変わる様子を、何度目にしたことだろう。まったく無表情だった少年が微笑み、はげしいチック症状がピタッと止まり、吃音が消え、ならず者のような子が自ら姿勢を正し、ひどく引っこみ思案の子が手を挙げ発言するようになった。魔法だった。奇跡だと思った。偶然だろう、と最初は思った。「なにかの加減で、たまたまうまくいっただけだ。いや、メンバーがよかったのだ」と自分に言い聞かせた。こんなミラクル、そうそう起こるものではない、と。 しかし、回を重ね、メンバーが変わっても、やっぱり同じことが繰り返し起きるのだ。『あふれでたのは やさしさだった 奈良少年刑務所 絵本と詩の教室』寮 美千子(2018)
この取り組みをどう世の中に伝えていけばいいのか、最初はただただ頭を抱えたし、今も難しいと感じている。少年たちが犯した罪によって苦しむ被害者の方がいるという事実を、加害者を支援する私たちも決して忘れてはいけない。
その上で、まだ長いこれからの人生を社会の中で生きていく少年たちが、夢や目標を捨てず、誰かの役に立つことにやりがいを感じ、社会に貢献する人になってくれたらと応援し続けたい。そう改めて思わせてくれた6人の少年に精一杯の感謝を伝え、2日間のプログラムが終了した。
–
ようやく第一歩を踏み出すことができた、HIGH HOPEプログラム。年内にテーマを変えてもう一度、多摩少年院で開催させていただきます。「絶望から希望を生む。つぶされた可能性に光を灯す。」このメッセージを体現できるよう、全力で進みます。
ICHI INC.